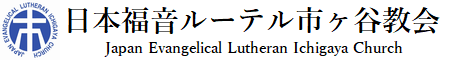説教「永遠のいのちが見える」
マルコ10:17~31
聖霊降臨後第21主日(2015年10月18日)
日本福音ルーテル市ヶ谷教会礼拝堂(東京都新宿区市谷砂土原町1-1)
牧師 浅野 直樹
「永遠の命を受け継ぐには、何をすればよいでしょうか」。ある人がこういう質問をイエスに向けました。同じ話はマタイ、ルカ福音書にもあります。マタイではこの人は青年となっています。ルカ福音書では議員と書いてあります。福音書によって、そうしたばらつきがありますが、そのことは今回、あまり重要ではありません。きょうの福音書でみなさんにぜひとも気にしていただきたいのは、永遠の命です。
永遠のいのちについて、みなさんは日頃考えたりすることはありますでしょうか。まずないと思うのです。お昼御飯をみんなで食べているときに、「ねえ、永遠のいのちってどう思う?」なんて話題を向けたら、キモッと言われてみんな席を離れるでしょう。話題にできないのです。あまりにも世間離れ、日常離れしていて、そんなこと考える気にもならない、考えてもしょうがない、普通はそう受け止められてしまいます。
永遠という言葉は、使わないわけではありません。いつまでも、ずっと。そういう日本語を少し固い表現で言い換えた言葉が永遠です。けれどもこれがいのちとくっついて永遠のいのちという言葉になると、ここから不協和音が生じます。なぜならいのちが永遠でないということをだれもが知っているからです。限りあるいのちと永遠という言葉をくっつけると、そこに矛盾が起こってしまうのです。
永遠のいのちとは、時間の問いではありません。いのちの問いです。わたしたちのいのちの正体が何か、どこからきてどこへ行くのか、そういう問いをしていくときに、永遠のいのちというものがあるのだろうかという素朴な問いなのです。こうして生活していて、いろんな出来事を知り見聞きしていると、いのちのはかなさを思い知らされます。そうすると永遠のいのちというものがどうしてあり得るのだろうかと感じさせられるのです。信じるという心と同時に疑うという心をも、わたしたちは持ち合わせていますので、いのちが次から次へと奪われていく悲しい出来事に触れるにつけ、「そんなものあるはずない」、人間の常識だけで推し量ろうとするとそういう答えしか出てきません。けれどもその一方で、自分自身の弱さ、人間の小ささや罪深さなどを思うと、頼りない頭で考えてそういうふうに決めつける自分にも自信が持てなくなります。
いのちについて、問うということを人間はやめてはならないと思うのです。尊いいのち、であるにもかかわらず、戦争やいじめが原因で、そのように扱われない、またいのちの尊さをよく分かっていない若者たちの信じられないような現実をみるにつけ、なぜ尊いのかをもっともっとわたしたちが語り、そして考えなければなりません。
いのちが地球よりも重たいといいますが、この言い方は永遠のいのちという言い方とよく似ています。いのちの尊さを重さで表現したのが前者で、時間で言いあらわしたのが永遠のいのちです。ですから永遠のいのちとは、時間で推し量ることができないほどの価値がいのちにはあるということを、まずもって言いあらわしています。けれどもそれだけではありません。それはきょうのイエスの言葉からわかります。
「永遠の命を受け継ぐには何をすればよいか」という問いに始まって、そこからイエスがモーセの十戒をとりあげて、「聖書にこう書いてある」というと、「先生、そういうことはみな、子どもの頃から守ってきました」と男が答えます。この男は金持ちだったようで、イエスがその男に、「持っているものを売り払い、わたしに従いなさい」というと、男は悲しげにその場を立ち去ったというお話です。そこから話はさらに展開していき、24節でイエスはこう言っています、「子たちよ、神の国に入るのは、なんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりも、らくだが針の穴を通る方がまだ易しい」。らくだが針の穴をくぐり抜けるなんてできっこない、そう思った弟子たちは、「それでは、だれが救われるのだろうか」と考えるのです。
永遠のいのちを受け継ぐ、これを言い換えたのがイエスが使った「神の国に入る」という言葉です。そして弟子たちは、これをもっと身近な言い方で端的にこう言っています。「だれが救われるのだろうか」。永遠のいのちを受け継ぐ、神の国に入る、そして救われる。この三つは表現の違いであって、指し示している出来事は同じです。たぶん、わたしたちに最も簡単なのはどれかといえば、やはり弟子たちと同じく「救われる」でしょう。ですから永遠のいのちについての議論は、唯単にいのちの尊厳について考えるだけでなくて、もう一歩踏み込んで「救われる」という別次元へと踏み込むことになるのです。いのちについては、このレベルまでほんとうは考えたいのです。考えるべきなのであります。けれどもそういう機会は普通はまずありません。教会だからこそ考えることができるのです。世間では白々しくなって声に出すこともできないけれど、実はわたしたちのだれもが真剣に考えてみなくてはならないテーマについて、イエスの言葉をもとに考えることができるというのは、すばらしい機会です。
永遠のいのちについて真剣に聞く、真剣に考える。わたしたちは今、神のみことばを前にしてそれをやっているのです。なんといってもイエス御自身が、この言葉をなんのてらいも無く使っています。そして議論しています。イエスにとって、この言葉は身構えることもない、ごく当たり前の普段着の言葉なのです。
物理学者たちは時間について真剣に考えます。科学的に究明します。するとどういう答えが返ってくるのでしょうか。物理学者が真剣に考えて出てくる答えというのは、一般のわたしたちからすると、ときにそれは禅の公案のようにも聞こえます。
時間の長さは絶対ではない、物理学者は時間についてそう答えるみたいです。一秒という時間の幅、これは決まっているではないかと思えるのですが、これは見る場所によって違ってくる、ということを物理学者は教えてくれます。また物理学者はこういう問いもしてきます。時間というのはほんとうに存在しているのだろうか。わたしたちは時間があると思って生活していますが、もしも宇宙からありとあらゆる物質が消えてなくなったら、それでも時間はあるだろうかと考えるわけです。地球も太陽もない、光もないとき、そのとき時間はあるだろうかと問うのです。あるという学者もいるし、ないという科学者もいるようです。
永遠は時間の無限の延長のようにも思えますが、そうではありません。永遠を考えるとき、まずは時間と切り離す必要があります。ですから、たとえ時間が存在しなくても永遠はそれによって消えることはありません。永遠は時間とも切り離して、まったく別次元のことがらとしてとらえる必要があるのです。
「持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。(そうすれば永遠のいのちを受け継ぐことができる)」、イエスは男にそのように告げました。貧しい人に施すために、自分のもっているものをすべて提供しなさい、捨てなさい。イエスはそれをわたしたちに言っているわけではなくて、「聖書に書いてあることは小さいときから全部守っています」という、とても熱心なユダヤ教徒にそういったのです。守ることは正しくきちんと守れても、人のために尽くすということをこの人は知らなかったのです。そしてそこに永遠のいのちに至るカギがあることを知らなかったのです。
ユダヤ人にとっての永遠を考えるとき、ぜひとも参考にしたいのが詩編136編です。少し引用しますと、「恵み深い主に感謝せよ。慈しみはとこしえに。神の中の神に感謝せよ。慈しみはとこしえに。主の中の主に感謝せよ。慈しみはとこしえに」。
こういう調子で最後までずっと、慈しみはとこしえに、というリフレインが続きます。この「とこしえに」は、永遠という意味でもあります。おもしろいことに、この「とこしえ」という言葉がヘブライ語聖書をみると複数形になっているのです。すなわち永遠が複数形なんです。こういう感覚は日本語にはありません。歴史を通してイスラエルの民をずっと導いてくださった神様に感謝をささげているこの136編なのですが、その都度その都度、そしてどこまでも神様は変わらぬ慈しみをわれらに注いでくださる、そんな歌です。永遠が、神様から人間に繰り返し注がれる恵みとして描かれているのが136編からわかります。
「もし一粒の麦が地に落ちて死ねば、豊かに実を結ぶ。自分の生命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む人は、それを保って永遠の命に至る」。ヨハネ福音書にある有名なイエスの言葉です。三浦綾子の小説「塩狩峠」の主人公や、ポーランドのコルベ神父の生涯を思い起こす言葉です。このみ言葉と、さきほどの金持ちの男に対して語ったイエスの言葉は、見事に重なってきます。一粒の麦が示しているのは、人を愛するということ、そのために自分を献げるということ。さきほどの詩編136編が示しているのは、神が人に向ける慈しみという、これもまた愛です。神の愛、そして人の愛。神が愛してくださる愛、人が隣人を愛する愛。いずれも同じひとつの愛、アガペーです。
永遠のいのちを考えるとき、やはり愛にたどり着くのです。愛というわざ、愛という力、エネルギーの中に永遠の次元があるのです。永遠のいのちを受け継ぐ、神の国に入る、救われる。この三つの表現がありましたが、もしもこれをまとめていうことが許されるなら、わたしはこう言いたいのです。永遠のいのちを生きる、神の国に入る、そして救われるとは、わたしたちが神様を愛するということ、わたしたちが互いに愛し合うということ、そのようにしてわたしたちが神のいのちを生きるということ、それが永遠のいのちを生きるということです。