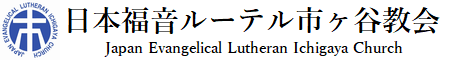説教「この人を見ないか」
ルカ7:36~50
聖霊降臨後第6主日(2016年6月26日)
日本福音ルーテル市ヶ谷教会礼拝堂(東京都新宿区市谷砂土原町1-1)
東谷清貴神学生(日本ルーテル神学校)
これが本当に、神の民イスラエルの王の姿なのでしょうか。
部下であるウリヤの妻、バト・シェバに目を留め、その美しさに惹かれたダビデは、彼女との情事に溺れました。やがて、自分の愛人となったバト・シェバが子を宿したことを知らされると、夫ウリヤを戦場の最前線に立たせるように命令したのです。ウリヤはそこで戦死します。ダビデは未亡人になったバト・シェバを、まんまと自分の家に引き取ったのです。イスラエルの王ダビデは、自分の部下の妻を寝取った上に、その部下を死に追いやりました。
そこにナタンという預言者が現れます。神の使いである預言者ナタンは、ダビデのところへ行き、ある事件を報告します。それは、旅人をもてなそうとした金持ちの男が、ありあまるほどいる自分の家畜の中から出すのを惜しんだ。そして貧しい者が大切にしていた、たった一匹の小羊を取ってもてなした、という事件でした。この話を聞いたダビデは激怒して、そんな男は死罪だ! 小羊の四倍の償いを払わせろ! と断罪します。
これに対しナタンが言った言葉が、「その男はあなただ」でした。ダビデに、お前こそ死刑ではないか、と言い放ったのです。ナタンはダビデの非道な行いを告発したのです。ナタンのこの言葉に、ダビデは目を覚まします。自分が死刑だと宣告した金持ちの男と、自分がまったく同じことをしていると、気付かされたからです。ダビデは唖然として、「わたしは主に罪を犯した」と告白しました。
ダビデの物語は、私たちに大きなショックを与えます。あのダビデでさえも、このような罪を犯してしまう。英雄的な活躍が称賛され、理想的な王として支持されたあのダビデですら、卑劣で残虐な行為に走ってしまったのです。
この出来事を契機に、ダビデの栄光を物語ってきたサムエル記は、暗転していきます。確かに罪を認めたダビデが、死刑になることはありませんでした。「主が罪を取り除かれる」とナタンが宣言した通り、生き長らえることが出来たのです。しかし、決して手放しで喜べることではありませんでした。
主の予告通り、この後、ダビデ王朝からは、悪を行う者が次から次へと起こされていきます。とりわけ、愛する息子アブサロムの反逆は、ダビデを打ちのめしました。王子アブサロムが、ダビデに対してクーデターを起こしたのです。彼はダビデの王宮と共に妻たちをも奪い取りました。ついに息子アブサロムと戦わざるを得なくなったとき、ダビデの絶望はどれだけ深いものだったでしょうか。アブサロムが討ち取られたという知らせに接したダビデは、くずおれ、息子アブサロムの名を絶叫した、と言います。
「その男はあなただ」というナタンの告発からダビデ王朝に陰りが生じました。サムエル記が描く王朝の歴史は、華やかな栄光の歴史ではなく、罪の歴史へと塗り替えられていきました。自らが起こした事件を契機に、ダビデの周囲は変わって行ったのです。情事が起こり、血の復讐が起こる。自分が犯した罪を子どもたちも犯すのを目の当たりにしたダビデは、震えが止まらなくなったかのように見えます。
私たちが驚かされるのは、貧しい男から一匹の羊を奪った金持ちの男の話を聞き、即座に死刑を宣告した正義感の強いダビデが、ナタンから指摘されるまでは、自分の罪に全く気付いていなかったという矛盾です。
ダビデは「死罪」ということに付け加えて、「小羊の償いに四倍の価を払うべきだ」とも言っていました。確かにこれは、出エジプト記にある、他人の家畜に害を与えたときの賠償規定なのです。そこには羊一匹の損失に対して羊四匹で賠償しなければならない、と明記してあります。ダビデは律法の規定に大変忠実であり、律法に基づいた正義感をあらわにしたのでした。
ところがそのダビデが、自分の罪に関しては、何一つ見えていなかったのです。他人の行為や事件は客観的に、冷静に見ることが出来るにもかかわらず、ひとたび自分が起こしていることとなると、何一つ気付くことが出来なかったのです。
この物語には、自分の視点からでは罪を自覚することができない人間の姿が見えるのではないでしょうか。
新共同訳聖書には、ダビデのしたことが、「主のみ心に適わなかった」と書かれていました。実は、旧約聖書のヘブライ語原典で、「主のみ心に」というのは、「主の目に」と書かれています。直訳してみれば「主の目に悪であった」と書かれているのです。ダビデのしたことは、「主の目に悪と映った」のです。
そのことは、ナタンの口を通して、ダビデにも伝えらます。あなたに油を注いでイスラエルの王としたのはわたしである。わたしがあなたを救い出し、あなたに家を、妻を与えてきたではないか。イスラエルとユダの国まで与えてきた。不足であったら何であれ付け加えたであろうとさえ神さまは言われます。
それなのに、なぜ主の言葉を侮り、わたしの意に背くことをしたのか。これが、神さまがナタンを通して語られた、ダビデに対する叱責でした。「なぜわたしの意に背くことをしたのか」。「わたしの意に」、つまり「神さまの意に」背いたとダビデは言われているわけです。
この新共同訳で神さまが言う「わたしの意に」、これも、ヘブライ語原典では「わたしの目に」と書かれています。神さまはダビデに向かって、「なぜわたしの目に悪と映ることを、あなたはしたのか」と問いかけておられるのです。このように神さまの「目」には、人間の悪を映し出す「裁きの眼差し」があるのです。
ダビデはハッとして我に返りました。羊飼いとして羊の番をしていた小さな自分が、神さまの目に留まり王に選び出されたときから始まって、自分の歩みがいつも神さまの目に映っていたことに気付いたからです。溢れるほどの恵みを与えられてきた中にも、祝福してくださっている神さまの眼差しが常にあったはずです。
しかし、神さまからの恵みも忘れて、あたかも自分の力でのし上がってきたかのように振る舞い始めたとき、神さまの目には悪と映っていたのです。ダビデには自分の行っている悪が、もはや自分ではわからなくなっています。人間の持っている目には、自分の姿や行いが、自分の都合の良いようにしか映らないからです。
今日の福音書に登場する、ファリサイ派の人にも同じことが言えるのではないでしょうか。
この人の家に招かれたイエスさまの足もとでは、町中の人から「罪深い女」と呼ばれる人がいました。「罪深い女」は、イエスさまの足を涙でぬらし、髪でぬぐい、接吻して香油を塗っていたと言います。
この両者に対するファリサイ派の人の眼差しは、終始批判的です。イエスさまを指して、「この人がもし預言者なら、自分に触れている女がだれで、どんな人かわかるはずだ。罪深い女なのに」と思ったと書かれています。つまり、この女性に対する社会的な見方そのままに、一方的で断罪的なのです。
ここには他人の罪を決めつけて、自分の罪深さを問うことが決してない、傲慢さがあります。他人を批判し、差別することで、自分の身を保ち、守ろうとする姿。自分が関わりたくない相手を排除する。これは、私たちにもあることではないでしょうか。
このファリサイ派の人に向かって、イエスさまは「この人を見ないか」と語りかけました。そこには溢れ出る涙をとめることもできず、イエスさまの足にしがみついている、一人の女性の姿がありました。
イエスさまがファリサイ派の人に突きつけたのは、このようなもてなしを、あなたは何一つしてくれなかったではないか、という疑問でした。ファリサイ派の人にはまったく見えていないものが、そこにはあるのではないか、という疑問でした。
罪の自覚のないところに、救いの出来事は見えません。むしろ自分の罪深さに打ちのめされた者の方にこそ、救いの出来事が起こっているのです。
この女性は、自分の罪の深さなら、嫌というほど自覚させられていたことでしょう。ファリサイ派の人に限らず、町中の人から差別的な発言や扱いを受けてきたに違いありません。周囲には常に冷たい視線があったことでしょう。その辛さに耐えながら生きてきた人生があったはずです。
しかしその辛さの中で、この女性とイエスさまとの出会いが起こったのです。この「罪深い」と呼ばれてきた女は、イエスさまの眼差しに、それまでに受けたことがない何かを感じたのではないでしょうか。自分を排除する視線ならいくらでも浴びてきたことでしょう。しかしイエスさまの眼差しは、慈しみと憐れみに満ちていました。
イエスさまは、「この人が多くの罪を赦されたことは、わたしに示した愛の大きさで分かる」と仰いました。人が背負いきれなくなった罪を、ただ一人十字架の上で贖ってくださった方からの深い慰めが、そこにはあります。
イエスさまにしがみつくしかなくなった人にこそ、救いの出来事が起こっているのです。
イエスさまはご自身を批判するファリサイ派の人を断罪されることもありませんでした。ダビデも神さまの眼差しを示されて、自分の罪に気付かされました。イエスさまは罪人を、罪深い者であるにもかかわらず、それでもなお赦そうとする憐れみを示してくださっているのです。
神さまの憐れみによって救いのあったところに、神さまの愛が溢れています。
イエスさまは私たちのことをいつも見守ってくださっています。私たちは、いつもイエスさまの目にある、慈しみと憐れみの眼差しのもとで、生かされているのです。